|
カテゴリ: |
2026-01-13 (Tue)
|
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
|
カテゴリ:高度系試験 |
2012-11-25 (Sun)
|
高度試験の共通午前Ⅰは、同じ日に実施される応用情報技術者試験の午前問題80問から、30問を抜き出したものです。抜き出しているなら出題傾向は同じかと思いますが、実は違うのです。ちょうど1年前のエントリでちらっと書きましたが、もう少し詳しく見てみましょう。
この図は、2009~2012年の8回分の試験での、「テーマ06 ハードウェア」の分野からの出題一覧です。
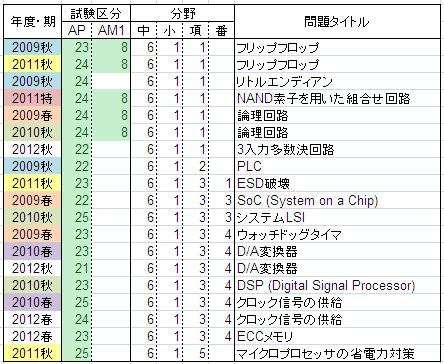
※AP=応用情報技術者、AM1=高度共通午前Ⅰで、試験区分欄の数字は問題番号を表しています。
※分野欄の数字は、IPAの応用情報技術者試験シラバス ver.2.0の出題分野を表しています。
これを見ると、応用情報の午前ではわりと幅広くハードウェアの問題が出ています。ところが、高度午前Ⅰは、たしかに応用情報の午前から抜き出されていますが、論理回路(順序回路、組合せ回路)から5回出題されているだけなのです。
つまり、高度午前Ⅰから受験する方は、ハードウェア分野に関しては、論理回路の過去問だけ勉強しておけば対応できます。PLCとかDSPは知識として知っていればもちろん有用ですが、限られた時間で試験対策する上では勉強しなくていいのです。
これ以外の分野でも、高度午前Ⅰと応用情報で出題傾向の違いがあります(違いのない分野もあります)。多くの参考書は「応用情報・高度午前」という感じのタイトルで、共通の内容になっていますが、これで高度午前Ⅰの勉強をすると無駄が多くなります。
そこで私の著書は、2013年版から高度午前によく出る分野に特化した内容に変えました。宣伝
この図は、2009~2012年の8回分の試験での、「テーマ06 ハードウェア」の分野からの出題一覧です。
※AP=応用情報技術者、AM1=高度共通午前Ⅰで、試験区分欄の数字は問題番号を表しています。
※分野欄の数字は、IPAの応用情報技術者試験シラバス ver.2.0の出題分野を表しています。
これを見ると、応用情報の午前ではわりと幅広くハードウェアの問題が出ています。ところが、高度午前Ⅰは、たしかに応用情報の午前から抜き出されていますが、論理回路(順序回路、組合せ回路)から5回出題されているだけなのです。
つまり、高度午前Ⅰから受験する方は、ハードウェア分野に関しては、論理回路の過去問だけ勉強しておけば対応できます。PLCとかDSPは知識として知っていればもちろん有用ですが、限られた時間で試験対策する上では勉強しなくていいのです。
これ以外の分野でも、高度午前Ⅰと応用情報で出題傾向の違いがあります(違いのない分野もあります)。多くの参考書は「応用情報・高度午前」という感じのタイトルで、共通の内容になっていますが、これで高度午前Ⅰの勉強をすると無駄が多くなります。
そこで私の著書は、2013年版から高度午前によく出る分野に特化した内容に変えました。宣伝

PR
|
カテゴリ:会社経営 |
2012-11-19 (Mon)
|
仕事の連絡で電話を使うことは多くないので、会社の電話機が鳴るとドキッとします。
珍しく電話機が鳴って手を伸ばそうとすると、ワンコールで切れてしまうことがあります。ワンコールで取っても、すでに切れています。1ヶ月に1~2回でしょうか、昼間だけでなく、深夜にもあります。
ナンバーディスプレイは契約していないし、うちはISDN回線なので136も使えず(アナログ回線から136にかけると、直前の着呼の発信者番号が分かります)、誰の仕業か分からずモヤモヤしていました。ナンバーディスプレイ利用者によると非通知でかかってくるそうなので、以前流行した折り返し電話させることを狙ったワン切り電話ではないようです。
いろいろ調べていたところ、電話番号の履歴を追跡調査して、その情報を売る会社があることが分かりました。例えば、クローバー・ネットワーク・コムという会社の“Doc Bell”というサービスです。
あらゆる電話番号に定期的に発呼して、応答状況を長期間にわたって蓄積していきます。そうすると、その電話番号がいつから使われているか、言い換えれば、個人がいつからそこに住んでいるか、会社がいつから営業しているかが分かります。電話が解約されれば、「現在使われておりません」とアナウンスされるので、転居や廃業が分かるでしょう。これは与信管理を必要とする会社にとって有用な情報となるはずです。
うちにかかってくるワン切り電話の真相は不明ですが、そういう調査の電話かもしれないと分かったので、少しすっきりしました。
珍しく電話機が鳴って手を伸ばそうとすると、ワンコールで切れてしまうことがあります。ワンコールで取っても、すでに切れています。1ヶ月に1~2回でしょうか、昼間だけでなく、深夜にもあります。
ナンバーディスプレイは契約していないし、うちはISDN回線なので136も使えず(アナログ回線から136にかけると、直前の着呼の発信者番号が分かります)、誰の仕業か分からずモヤモヤしていました。ナンバーディスプレイ利用者によると非通知でかかってくるそうなので、以前流行した折り返し電話させることを狙ったワン切り電話ではないようです。
いろいろ調べていたところ、電話番号の履歴を追跡調査して、その情報を売る会社があることが分かりました。例えば、クローバー・ネットワーク・コムという会社の“Doc Bell”というサービスです。
あらゆる電話番号に定期的に発呼して、応答状況を長期間にわたって蓄積していきます。そうすると、その電話番号がいつから使われているか、言い換えれば、個人がいつからそこに住んでいるか、会社がいつから営業しているかが分かります。電話が解約されれば、「現在使われておりません」とアナウンスされるので、転居や廃業が分かるでしょう。これは与信管理を必要とする会社にとって有用な情報となるはずです。
うちにかかってくるワン切り電話の真相は不明ですが、そういう調査の電話かもしれないと分かったので、少しすっきりしました。
|
カテゴリ:【AP】応用情報技術者 |
2012-11-16 (Fri)
|
2012年度春期・応用情報技術者試験の午前問3に、このような問題が出ました。2005年度秋期・ソフトウェア開発技術者試験の午前問7でも出題されていて、その再出題です。
|
次のBNFで定義される<DNA>に合致するものはどれか。 <DNA>::=<コドン>|<DNA>|<コドン> <コドン>::=<塩基><塩基><塩基> <塩基>::=A|T|G|C ア AC イ ACGCG ウ AGC エ ATGC |
BNF(バッカス・ナウア記法)は定番の問題です。ただ、題材に生物学の用語を持ち出しているところが珍しいです。私もかつてこの分野を学びましたので、どんな経歴の試験委員が作問したのだろうと興味があります。
コドンはDNAの塩基3つからなる配列で、それにアミノ酸が対応しています。AGC(アデニン、グアニン、シトシン)は、セリンというアミノ酸に対応します。正解はウです。
|
カテゴリ:中小企業診断士 |
2012-11-04 (Sun)
|
また、先日の中小企業診断士2次試験のネタです。
事例Ⅳ(財務)は、計算問題が大量に出た中で、最後の第3問(設問2)だけが記述問題でした。簡単に言うと、オーナー夫妻が経営する温泉旅館で、経営を引き継ぐ子供も親族もいないが、誰に経営を引く継ぐのがよいか、また留意点は何か、を200字で書かせる設問です。問題冊子は、こちらです。
資格対策教育の各社から出た解答速報では概ね、従業員に承継する案と、周辺旅館など同業他社に承継する案が挙げられています。留意点としては、この旅館のコンセプトの維持であるとか、従業員雇用の継続などが挙がっています。
今日、東京・神田の日本マンパワーの2次解説会に参加して、モデル解答を受け取ってきました。
事例Ⅳ(財務)は、計算問題が大量に出た中で、最後の第3問(設問2)だけが記述問題でした。簡単に言うと、オーナー夫妻が経営する温泉旅館で、経営を引き継ぐ子供も親族もいないが、誰に経営を引く継ぐのがよいか、また留意点は何か、を200字で書かせる設問です。問題冊子は、こちらです。
資格対策教育の各社から出た解答速報では概ね、従業員に承継する案と、周辺旅館など同業他社に承継する案が挙げられています。留意点としては、この旅館のコンセプトの維持であるとか、従業員雇用の継続などが挙がっています。
今日、東京・神田の日本マンパワーの2次解説会に参加して、モデル解答を受け取ってきました。
●日本マンパワー
|
承継先としては、D旅館の現従業員や周辺旅館が考えられる。
留意点としては、
①関係者の理解
②従業員の場合は経営者教育、
③株式の売却、
④個人保証・担保の取り扱い、等がある。
特に当社の場合、企業価値が約9.2億円あり、有利子負債が約4.5億円、株式価値が約4.7億円のため、前述③④に留意すべきである。
これらは中小企業承継円滑化法により、日本公庫や保証協会によるEBO特例等もあり、その活用も留意すべきである。
|
いかがですか。これはなかなかすごい解答例です。
事例Ⅳは財務なので、前問までの内容を踏まえて、財務の観点で具体的な数字を使って解答しています。中小企業は社長が会社債務を個人連帯保証していることが多いので、金融機関に対して「社長が変わりますので、よろしく」では済まない点に触れています。中小企業承継円滑化法にも触れています。
ほとんど税理士の仕事じゃないかと思うくらいです。あるいは、金融機関での勤務経験があれば、さらっと出てくることかもしれません。こういう視点を持つことは大切だと思いますが、私のようなIT系の診断士受験生には厳しいレベルですね。私は、同業他社への承継だけ書いて、200字で延々と説明してしまいました。
※日本マンパワー以外の各社からの解答例は、[…続き] をクリックすると表示されます。
|
カテゴリ:中小企業診断士 |
2012-10-29 (Mon)
|
2012年10月21日に中小企業診断士2次試験を受けてきました。資格学校各社の解答速報や分析資料もだいぶ出揃いました。
私には、言うのも恥ずかしいくらい、多くの2次試験の不合格経験があります。なんせ1次試験の初合格は、10年前の2002年ですから。2次試験を受けたのは5年ぶりで、その当時はまだ会社に勤めていました。
その2007年末で退職して独立したので、独立以来初めての2次試験でした。5年間のブランクでだめかなと思ったら、感想は「意外とできた」です。解答速報を見る感じでは、大きく外している感じはありません。ここを押さえればいいという視点は合っています。5年前までの試験では、解答速報を見れば理解できるが、試験の時は大外ししてしまうことが多かったです。
この5年間、資格学校を利用したわけでもなく、独学で勉強に打ち込んだわけでもありません。でも、独立して経験したことが、いろいろ勉強になったなと感じます。今年こそ合格していればと期待を込めて、12月7日を待ちたいと思います。
【追記】 2次筆記試験は合格しました。
私には、言うのも恥ずかしいくらい、多くの2次試験の不合格経験があります。なんせ1次試験の初合格は、10年前の2002年ですから。2次試験を受けたのは5年ぶりで、その当時はまだ会社に勤めていました。
その2007年末で退職して独立したので、独立以来初めての2次試験でした。5年間のブランクでだめかなと思ったら、感想は「意外とできた」です。解答速報を見る感じでは、大きく外している感じはありません。ここを押さえればいいという視点は合っています。5年前までの試験では、解答速報を見れば理解できるが、試験の時は大外ししてしまうことが多かったです。
この5年間、資格学校を利用したわけでもなく、独学で勉強に打ち込んだわけでもありません。でも、独立して経験したことが、いろいろ勉強になったなと感じます。今年こそ合格していればと期待を込めて、12月7日を待ちたいと思います。
【追記】 2次筆記試験は合格しました。
|
カテゴリ:中小企業診断士 |
2012-10-27 (Sat)
|
先週10月21日(日)は秋の情報処理試験の日でしたが、私は同じ日にあった中小企業診断士2次試験を受験していました。
その事例2で、「コーズリレーテッドマーケティング」なる言葉が登場して、受験生を大いに困らせたようなのです。マーケティング分野でCRMと言えば“Customer Relationship Management”ですが、“Cause Related Marketing”も略せば同じCRMです。
 某資格学校の2次試験解説会でも、講師自身も知らなかった(その講師も実際に受験したそうですが、答を間違えた)と話していました。
某資格学校の2次試験解説会でも、講師自身も知らなかった(その講師も実際に受験したそうですが、答を間違えた)と話していました。
私も全然知らなかったのですが、与件文を読み込んで、「企業が売上の一部を社会貢献活動に寄付することで、企業イメージの向上を図ること」ではないかと推測して解答したところ、結果的にそれで正解でした。ヤマト運輸が宅急便1個に付き、10円を東日本大震災の被災地に寄付する活動をしていましたが、まさにそれです。
来年以降のITストラテジスト試験の午前2で出題されるかも知れませんし、ちょっと知っておくと得するかも。
その事例2で、「コーズリレーテッドマーケティング」なる言葉が登場して、受験生を大いに困らせたようなのです。マーケティング分野でCRMと言えば“Customer Relationship Management”ですが、“Cause Related Marketing”も略せば同じCRMです。
私も全然知らなかったのですが、与件文を読み込んで、「企業が売上の一部を社会貢献活動に寄付することで、企業イメージの向上を図ること」ではないかと推測して解答したところ、結果的にそれで正解でした。ヤマト運輸が宅急便1個に付き、10円を東日本大震災の被災地に寄付する活動をしていましたが、まさにそれです。
来年以降のITストラテジスト試験の午前2で出題されるかも知れませんし、ちょっと知っておくと得するかも。
|
カテゴリ:【AP】応用情報技術者 |
2012-10-23 (Tue)
|
応用情報技術者試験の午後の問1は経営戦略の出題になっていて、問2のプログラミングとどちらか選択します。
これまでの問1の出題テーマは、こんな感じです。
| 2009年 春期 | マーケティング戦略の立案 |
| 2009年 秋期 | ソフトウェアの受託開発会社における、工事進行基準適用 |
| 2010年 春期 | 企業の経営分析 |
| 2010年 秋期 | 販売戦略 |
| 2011年 特別 | 業務のアウトソーシング |
| 2011年 秋期 | 家電量販店の営業戦略の策定 |
| 2012年 春期 | ロジカルシンキングによる販売戦略立案 |
| 2012年 秋期 | M&A戦略 |
これまでは個別の機能戦略が中心でしたが、今回(2012年秋期)はM&A(合併と買収)という全社戦略です。飲料メーカーが同業他社を買収するストーリーで、簡単な財務諸表を見せて買収先の企業価値を算定させる内容です。
IT企業勤務の若い人には難解だったと思います。それこそ、中小企業診断士2次試験の事例Ⅳを易しくしたような内容ですから、面食らったのではないでしょうか。
この試験を受ける人の7割方はIT関連の社会人で、30歳までの人がメインです。プログラミングを選ぶ人が多いかと思いきや、私が仕事を通じて知るところでは、経営戦略を選ぶ人が7~8割を占めるようです。プログラミングは試験本番でテンパると全滅のリスクが高いので、日本語を読んで理解できそうな経営戦略に流れるのだと思います。問1を難しくして、問2のプログラミングを選ぶ人を増やそうという、IPAの策略でしょうか?
|
プロフィール
|
HN:
Keiji
性別:
非公開
|
カレンダー
|
|
カテゴリー
|
|
アーカイブ
|
|
最新コメント
|
|
ブログ内検索
|
|
カウンター
|
|
アクセス解析
|
